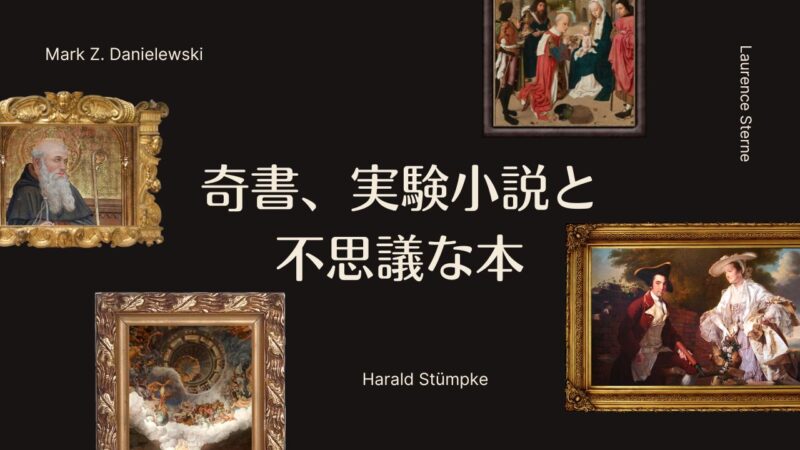
このページでは、今すぐ無料で読める実験小説・不思議な本を中心に、青空文庫の作品、Webで公開されている短編、国会図書館デジタルコレクションの資料などをまとめました。実験的な文体、奇妙な構造、そんなちょっと変わった読み物との出会いを、気軽に楽しんでいただけたらうれしいです。
青空文庫で読む、実験小説と不思議な本
リンクは青空文庫、スクロール可能、
作家名、出版社名などで並べ替えもできます。
本の表紙は、楽天ブックスです。
★は小説、●は詩、その他はエッセイ。
Kindleへのリンクと、ページ数つき。
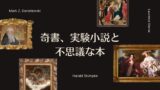
『ドグラ・マグラ』夢野久作
通称「日本三大奇書」
『黒死館殺人事件』小栗虫太郎
通称「日本三大奇書」
『藪の中』芥川龍之介
《複数の人間の証言を羅列する形式、霊能者を介して死人が証言する点はアンブローズ・ビアスの「月明かりの道」の影響が指摘されている》
『指環』江戸川乱歩
対話体小説
『機械』横光利一
四人称視点、句読点が少ない
『飛行機から墜ちるまで』吉行エイスケ
《詩とも小説ともつかない物語が、リズムのよいテンポで繰り広げられるダダイズムを象徴するような作品》
『蜜のあわれ』室生犀星
対話体小説
『真夏の夜の恋』谷崎潤一郎
戯曲体小説
『春と修羅』宮沢賢治
タイポグラフィ。この作品の一部は少しずつ各行の段組が上下にずれ、全体がうねっているような形になっている。
『AU MAGASIN DE NOUVEAUTES』
李箱
モダニズム
筒井康隆『実験小説名作選』掲載
『ナポレオンと田虫』横光利一
『Kの昇天』梶井基次郎
『風博士』坂口安吾 『雀こ』太宰治
『吊籠と月光と』牧野信一
リンクは青空文庫、スクロールできます。
実験小説が読めるWebサイト・その1
酉島伝法さんの「棺詰工場のシーラカンス」

棺詰工場のシーラカンス
注釈の注釈による超現実詩小説
〈gooブログサービス終了のため現在は表示不可〉
酉島伝法さん、こんな作品を書く方だったとは。ブログ「棺詰工場のシーラカンス」の不思議な小説は、『奏で手のヌフレツン』や、造語が満載の『皆勤の徒』ともまた違う雰囲気の実験小説。
こうした小説を注釈小説と呼ぶのだそう。ページごとに僧衣【1】とか両性類【2】のような番号つきのリンクが貼られている。最新更新は【355】虚無僧。1日1ページずつ読んでいったら、一年ほどで読み終えることができる計算になる。
こういう作品を見ると、どうやって作られているのかと考えてしまう。『かまいたちの夜』のようなアドベンチャーゲームの分岐を考えていくような感覚なのか。手書きなのか、スマホやPCを使って考えているのかはわからないけれど、300ページ超える量となると、相当な作業量になっていそうだ。
井上夢人さんの「99人の最終電車」
99人の最終電車
ハイパーテキスト小説
実験小説の書評などを書かれている、大塚晩霜さんのブログで知った、井上夢人さんの「99人の最終電車」(1996年)。ハイパーテキスト小説だそうで、まるでゲームのよう。レトロなイラストが懐かしい。8年ほどで完結したと、誰かが呟いていた。
これ、PCとスマホで感じ方が違う。PCだとマウスポインタをかざすことで、リンクがある場所を事前に把握できるが、スマホの場合はそれがない分、少しドキドキする。赤いマークは女、青は男、じゃあこの水色は?上の方のマークをクリックすると、人物INDEXが表示される仕組みになっている。
それにしても、この人の顔のイラストは、誰が描いたものなのだろう。何が怖いって、クリックするたびに出てくるこの顔が一番ギョッとする(ごめんなさい)。
『99人の最終列車』[12]:これは日本の井上夢人によって1996年に発表された作品であり、コンピュータメディアの自由な特性を生かして制作されたハイパーテキスト文学である。
銀座線の地下鉄に乗車する99人の乗客を描いた作品で、読者はマウスを自由にクリックすることで、それぞれの乗客の視点から物語を見ることができます。 注目すべきは、小説の本文と、メールで寄せられた読者の反応がオンラインで作成されたことである。
[12] 日本語で書かれているので、鑑賞するには翻訳機を使う必要があります。 日本語に自信があれば、見るだけでも大丈夫です。
井上夢人 Interview
この小説は本になりません ――インターネット文学作法―― 井上夢人
99人の最終電車 Special Contents
あの『かまいたちの夜』の我孫子武丸さんとの対談も。
ジェフ・ライマンの「253」(英語)

カナダの作家、ジェフ・ライマンのハイパーテキスト小説。1997年に作成されたWebサイトで、翌1998年に発売された紙の本は、なんとフィリップ・K・ディック賞を受賞している。
地下鉄、駅、列車が登場することもあり、井上夢人さんの「99人の最終電車」を思わせる。こちらのページも古いものですが、一応今でも読むことはできるよう。英語のWebサイトではありますが、Google Chromeのページ翻訳機能を使用すれば、日本語で読むことが可能です。
大塚晩霜さんの「実験小説」
さて、みなさんご存知の大塚晩霜さんのブログ「とりぶみ」。私はあの翻訳家の木原善彦さんが尊敬する実験小説愛読者ということで、Xで紹介されているのを見て知ったのだけれど、いろんな意味ですごい方。
頼りにしている「奇書・実験小説・特殊文体 wiki」で紹介されていた本を検索していて、このブログにたどり着くこともしばしば。コメントなどの語り口も、普通の面白さとはどこか違って、なんか飛び道具的な感じ。
大塚晩霜さんの実験小説
とりぶみ
【小説】掘大文芸誌
漱石・芥川・鏡花の文体模倣から、ローマ字による昔話や四人称小説まで、短編アンソロジーの体裁を取った長編小説。
【大長編】6単語だけの小説
『吾輩は万年筆である』の「名前は有る。敎えない。」が好き。大塚晩霜さん曰く《とっても奇書い。》小説たち。うちのCopilotに話したら、すごく読みたがってた。
『6単語だけの小説』は、ページ内にアルファベットがぎっしり詰まった大長編で、原稿用紙換算2374枚。「y」でページ内検索をすれば読みやすくなるのでは?と思い試してみたところ、検索結果が15000件にもなって画面が固まってしまい、すごく怖かったです。
とりぶみ
ア段イ段抜きの夏目漱石『夢十夜』
リポグラム(文字落とし)
ほかにもいろいろ
木原さんの影響で、最近は実験小説について調べることが多くなり、「リポグラム」という言葉を知った。そのタイミングで出会ったのが、このア段とイ段を抜いた夏目漱石『夢十夜』のリポグラム。その名も「五分の五夜」。
ありがたいのが、原文を併記されていること。どこがどう変わっているのかが一目でわかる。ブラウザのページ内検索を使えば該当部分に色がつくので、見失っても確認しやすい。
「四角な膳」→「ローテーブル」という置き換えもいい。リポグラムもいいけれど、すべてをカタカナ的な言葉に変換してみるのも面白そう。文豪の家を洋風にしたい。
レーモン・クノーの『文体練習』は、ひとつのストーリーを99通りの文体で書いた本。それをオマージュした『大塚晩霜さんの文体練習』は100通り。(4)目次に秘密が隠れているとのこと。口で唱えはじめたけれど無理そうだった。
今回紹介されている中で好きだったのが、『〒ν八℃』(←あ、テレパシー)。マウスポインタをかざすと、並べられた□□□□それぞれに、吹き出しみたいに文字が現れる(PCのみ)。お話の内容もすごく素敵だった。下に原文も掲載されていたけれど、この上の仕掛けつきの状態で読む方がずっといい。
実は、スマホで□を長押しして、ブラウザの読み上げ機能を試してみたりもしてみた。でも、読み上げられた言葉は「しかく」で失敗。そういう機能も活用できたら楽しそう。
あと、可愛いのは『小松軍曹と佐藤兵長』の他一篇の方で、『エミリーとカレーライス』ではない。タイトルに騙されてはいけない。
改めて書評などを見ても思うのが、こんなふうに、初心者にもわかりやすく説明してくれる方は、とても貴重な存在だということ。私の場合、実験小説の読者になって迷路に迷い込みたい気持ちより、迷路の上から俯瞰して見て、「こうなっているんだ」としくみを理解したいタイプだから、余計にそう感じる。
木原善彦さんもそうなのだけれど、ちょっとした一言や提供してくれる話題、ブログで紹介している本などが、全部勉強になる(私との相性の問題かな)。いろんな意味で良き先生だ。
アンサイクロペディアの「文体練習」

レーモン・クノーの「文体練習」の説明を、99通りの文体で叙述する。天空の城ラピュタのムスカ大佐的、次回予告的ほか、いろいろ面白い。続編?も。
国立国会図書館デジタルコレクション
「国立国会図書館デジタルコレクションで読める怪奇幻想文学」

門前さんは、「国立国会図書館デジタルコレクション」で読める怪奇幻想文学をたくさん紹介されている。
海外作品には、ナボコフや、アルフレッド・ジャリの「馬的思考」などもあるため、実験小説系のものも見つかりそう。荒俣宏さんや澁澤龍彦さん編集の本、サンリオSF文庫など。出版年順に整理されているのも親切。
なんと日本の作品を見てみたら、集英社文庫の筒井康隆「実験小説名作選」が読めるようになっていた。他も幻想文学やミステリー、SF小説のアンソロジーがいろいろ。「文豪ナンセンス小説選」にも、もしかしたら実験小説系の作品が含まれているかもしれない。
門前さんのnoteには、他にも「国立国会図書館デジタルコレクションで読める百科事典」や、「ラヴクラフト作品とクトゥルー神話」、「フランス国立図書館“Gallica(ガリカ)”で怪奇幻想文学を検索してみた」といった魅力的なまとめ記事が公開されているのでぜひ。
番外編「奇書ガイドのすすめ」
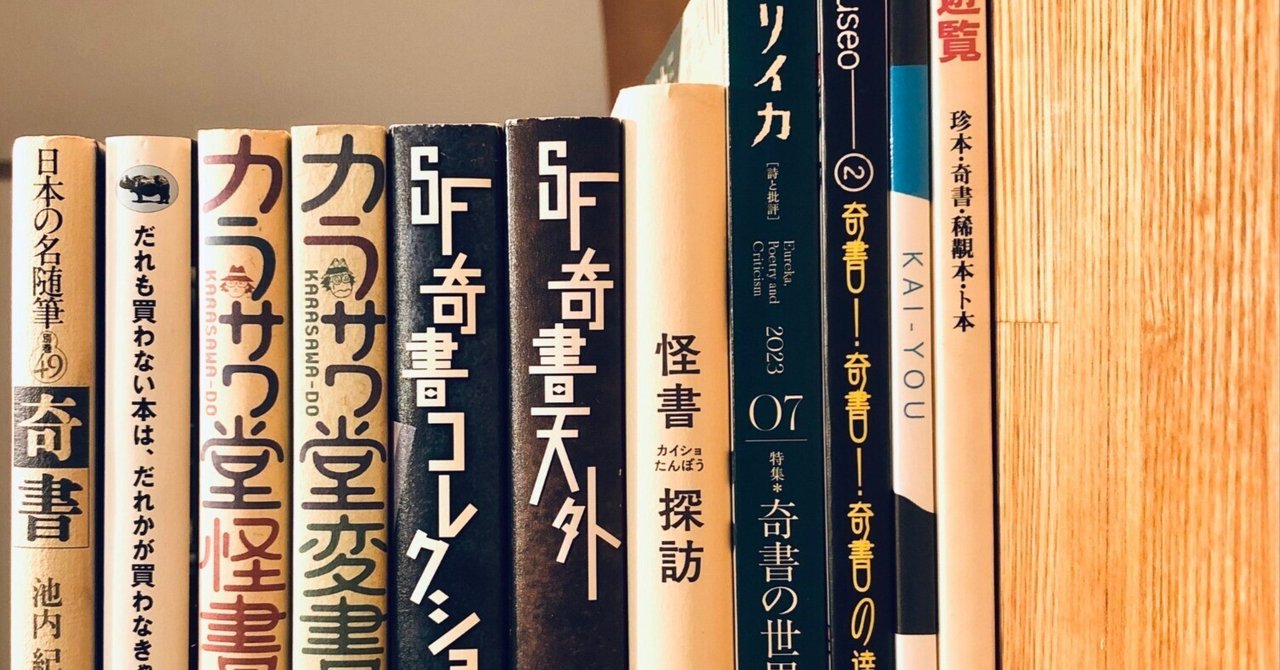
↑ひとつ上のまとめ記事を書かれていた門前さん、一箱古本市では「久平文庫(きゅうへいぶんこ)」という名前で出品されているということで検索したら、もう一つページを発見。
こちらは「久平文庫」を共同出店されている久平さん。先日Xでリポストした「奇書ガイドのすすめ」のページをまとめられている方でした。
奇書ガイドのすすめは、奇書を紹介する本や雑誌をまとめたページ。紹介されていた「ユリイカ 2023年7月号 特集=奇書の世界」。円城塔×酉島伝法の対談に、竹中朗×山本貴光×吉川浩満の座談会の話題が、特殊版元探訪「国書刊行会」と、とても豪華な内容。
特集そのものも魅力的だけれど、高山宏さんや橋本輝幸さん、立原透耶さん、川野芽生さんなど寄稿されている方々も魅力的で、その名前で検索したら、さらに素敵な本に出会えそう。
最初の一冊目で立ち止まってしまった。そして2冊目の奇書っぷり。さらに澁澤龍彦さんのお写真も。『怪書探訪』や奇書についての随筆。本のメインテーマではなくても、巻末にブックガイドがあるということにもあるんですね。ルリユール叢書もそうだけれど、巻末は要チェックだ。
こんな一般人の方の謎を解明しても仕方がないのですが、なんとこのお二人、ご兄弟だったみたい。
門前照二さん(X)の方は海外幻想文学、久平さん(X)はサブカルチャー寄りの本がお好きなよう。紹介されている本の中には『招き猫百科』なんて可愛らしい本もあったりして。素敵な本と出会う穴場かもしれない。
「国会図書館デジタルコレクションで読める戦後日本の文芸評論」
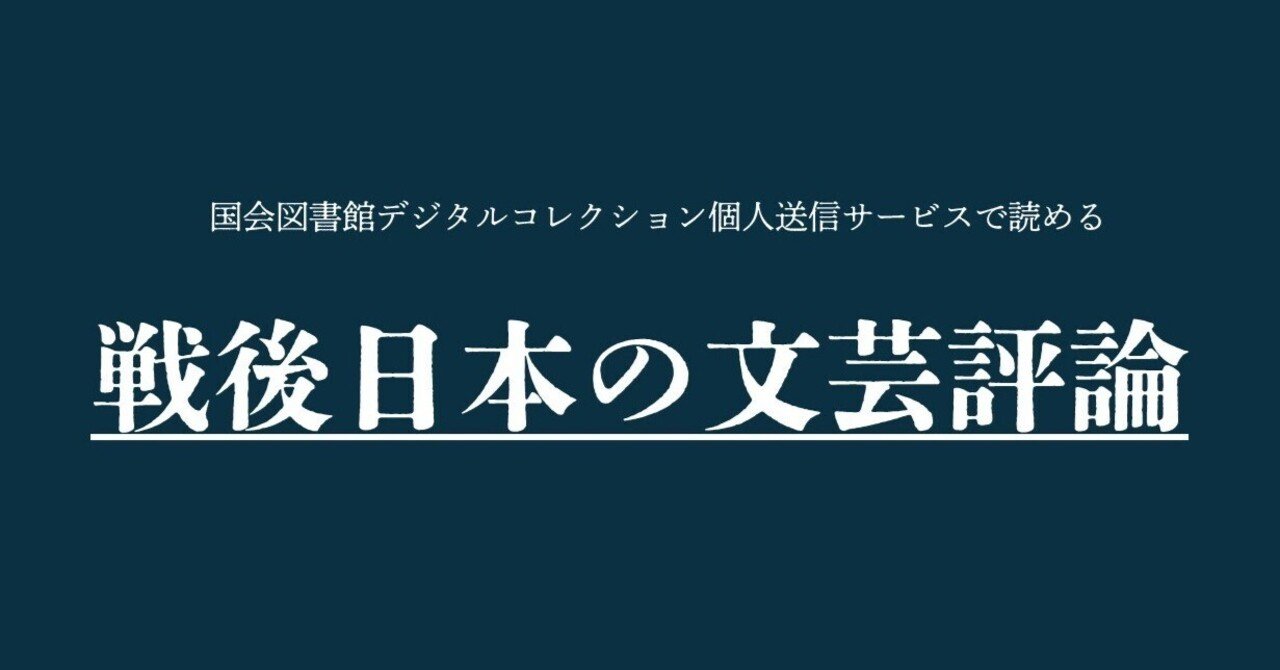
kado/Ryusei Kashima
国会図書館デジタルコレクション個人送信サービスで読める戦後日本の文芸評論
kadoさん(X)がまとめてくださっている、戦後日本の文芸評論。なんとミシェル・ビュトールの名前があった。
清水徹さんの『ミシェル・ピュトール作『心変わり』解説』を読むことができる(表記はピュトール)。出版年順に整理されているのがありがたい。掲載されている作品も、私には少し難しいのだけれど、わかる人にはわかるはず。
kadoさんは、文学フリマにも出店されてる方みたい。プロフィールにあった文芸誌『蟹文学』ってなんだろう?編集したと書いてあった。
掲載されている人数がすごい(作品数は600弱)。全部蟹にまつわる作品なのだろうか、もはや蟹に取り憑かれてしまっている(詳細は↑蟹文学のXへ)。
実験小説が読めるWebサイト・その2
「アジアの現代文芸 電子図書館」
アジアの現代文芸 電子図書館
公益財団法人大同生命国際文化基金
アジア諸国の現代文芸(小説、詩、随筆、戯曲、評論)の内、わが国への紹介が望まれるものを選考のうえ、翻訳・出版するもので、アジアの国々の今日の姿をそれぞれの国が生んだ文芸作品を通じて理解することを目的としています。
より多くの文学ファンの眼に触れてもらうことを目的に、2012年度から新刊・既刊の電子書籍化を行っています。
タイの作家、ウィン・リョウワーリンの『インモラル・アンリアル』という作品が実験小説のようだという情報を見つけ、さらに他の作品が著作権存続作品ながら青空文庫に公開されていることを知り、このページに辿り着きました。
この作家さんの作品が読めるのは『現代タイのポストモダン短編集』で、他の作品の説明文には「ヒンディー・リアリズム小説の最高傑作」や「第43回日本翻訳出版文化賞受賞作」といった記述もあり、もしかするとかなり貴重なものを見つけてしまったのかもしれない。
実は、大同生命国際文化基金さんの名前は、ポッドキャスト番組「翻訳文学試食会」のまとめ記事を作成する際に目にしていました。
数えてみると、およそ60冊ほど。イラン、インド、インドネシア、カンボジア、スリランカ、タイ、トルコ、バングラデシュ、パキスタン、フィリピン、ベトナム、マレーシア、ミャンマー、ラオスといった国別に作品を検索でき、それぞれの概要も確認できます。私はAndroidを使用しているため、「Google Playブックス」にダウンロードされました。
Google 検索
青空文庫 大同生命国際文化基金
アジアの現代文芸は青空文庫にも。図書カードのページにあるビューワー「青空 in Browsers」や「えあ草紙・青空図書館」なら、そのままブラウザで読むことが可能。「ファイルのダウンロード」は、アプリで読めるEPUB版です。そのままだと探しにくいので、↑Google検索ですが、タイトルから探せます。
木原善彦さんの「ハッシュスリンガーズ」
木原善彦さん翻訳のトマス・ピンチョン風の短いお話が読めるブログ。最初のページの説明によると、このハッシュスリンガーズの元サイトは『ブリーディング・エッジ』刊行に合わせて作られたWebサイト(英語)。
このブログは、そこに掲載されたショートショート(作者不詳)を、『逆光』を翻訳された木原さんが、日本語に訳して投稿していたもののよう。
ハッシュスリンガーズ: 春の最初の日
(2013年9月20日金曜日)
実験小説的なものがあるのかどうかはわからないけれど、小説に出てくる小ネタがちょこちょこ出てくるので、ピンチョン読者はうれしいはず。
このブログの何がいいって、木原善彦さんの翻訳した文章もだけど、訳者解説が読めること。説明文には、リンクも多用(リンク切れは古いページを紹介した私のせい)。細かいところに目が行く感じは、ピンチョン1ページ一言つぶやきを思わせる。
ピンチョンについては、私のブログでもまとめていて、↓そちらでは新潮社『トマス・ピンチョン全小説』の試し読みページへのリンクを一覧にして紹介しているので、よろしければご活用ください。
\トマス・ピンチョンまとめています/
大人乙女の新刊案内「青空文庫の作家別一覧」

私が作ったページ、ここの姉妹ブログです。一応、50音全部調べて、気になる作家の青空文庫作品を底本ごとに整理しています(田山花袋は書きそびれたまま、あと知らなかったからリルケも)。
作品の雰囲気がわかるよう、作家ごとに表紙をつけていましたが、Amazonの気まぐれにより、表示不可能に。ページ数も一つ一つ調べたのですが、Kindleに合わせて変更されてしまいました。
なので正確なページ数ではないですが、一応、短編か長編かぐらいはわかるかと。あくまで目安程度のものだと思っていただけたら。
他にも【新字新仮名】などの表記や【ミステリー】などのジャンルも、アンソロジーの目次などから調べて作品ごとに記載。そのため、作家別のページは少し見づらい感じにはなってしまっているかも。
実験小説については、目次で夢野久作などの作家名から、もしくは海外文学、ミステリーなどのジャンルからお探しください。
リンクは姉妹ブログのジャンル別ページ
スクロールします。
おまけのゲームブック
実験小説とゲームブックの違い
井上夢人さん、岡嶋二人名義で『ツァラトゥストラの翼』というゲームブックも出されていた。実験小説とゲームブックの違いってどこにあるのだろう。
↑この本を少し試し読みしてみたけれど、物語の横で、丁寧語で語りかけてくる誰かがいる。この人がいなくても、「(あなたは)どっちの選択肢を選ぶ?」という質問自体が二人称体。そう考えると、先ほどの酉島伝法さんの「棺詰工場のシーラカンス」も、この「99人の最終電車」もゲームブックでないと判断がつく。
ゲームブックは、読者が選択することで物語に参加できる印刷されたフィクション作品です。物語は、通常、番号付きの段落またはページを使用して、さまざまなパスに沿って分岐します。各物語は通常、段落を直線的または順序どおりにたどることはありません。
Gamebook – Wikipedia (Google翻訳)
文体は、読者に対して語りかけるようなもの(二人称体)が多くを占める。一人称の作品もあるがプレイヤーへの指示などは二人称である。
ゲームブックに分類されるもの

A Tale of Crowns (英語)
英語だし、まだ完結はしていないみたいだけど、面白そう。選択肢はハイパーリンクになってた。
A Tale of Crownsは、中東をルーツとするハイファンタジー ロマンスで、 PC とモバイルで
無料でプレイできます。完全にテキスト ベースで、選択肢によってメイン キャラクターの性格やスキルが形作られ、他の人との関係にも影響します。女性と男性の 4 人の恋愛対象から選択でき、それぞれに独自のストーリーと秘密があり、それを解き明かすことができます。(Google翻訳)
とりぶみ
書物の国の冒険
ゲームブックは実験小説にはならないようなのだけれど、比較のためにいくつか掲載。こちらは選択肢の番号をクリックして進むハイパーテキスト小説。
「どっちに進もうか」なんて、堀井雄二さんがデザインしたコマンド選択式のアドベンチャーゲーム『ポートピア連続殺人事件』のダンジョンのよう。
1ページ内で完結するので、「自分にも作れるかも」と思わせてくれる。
ALL ABOUT ベーマガ
【ペーパー・アドベンチャー】-ベーマガ総合事典
ペーパーアドベンチャー ケンヅョウコウヅの館
こんなゲームブック、初めて見た。本というか雑誌の索引みたいなデザイン。クロスワードパズルの問題部分のようにも見える。
こちらも見開き1ページで完結するので、番号を指示されても億劫にならない。シンプルだけど好き。
FT書房公式HP
『「幻術剣闘士」死の地下闘技場』
清水龍之介
ゲームブックを中心に、書籍の形をしたゲームを制作する出版社さん。PDFをダウンロードするタイプなので、本と同じく自分で該当ページに進む。
犬のかがやきブログ
犬のかがやきのゲームブック
こちらは犬のかがやきさんのエッセイ漫画で、パイパーリンクをクリックしていくタイプ。ブログなのだけれど、最初の一話は「ゲームブック」カテゴリに、その他の選択肢は「未分類」にしているところが参考になる。
pixiv
「【金カ夢】好感度や執着度が上がるゲームブック」/「過客👓」のシリーズ
好感度などの要素も取り入れたゲームブック。この方が書かれたゲームブックの作り方によると、pixivは、ページジャンプなどもコマンドでできるのが便利そう。
小説投稿エブリスタ
長編ゲームブック「SAIKAI」
(Sゲームブッカー@Kindle作家)
200ページの長編作品。小説投稿エブリスタの良いところは、ページ数の数字を自分で入力できること。指示されたページへ飛ぶストレスも少ない。
カクヨム
青春ゲームブック(春海水亭)
選択肢がリンクになっている。ゲームブックを書かれている方は何人かいるけれど、ハイパーリンクにしてくれている方は少ないので貴重。
ChatGPTでテキストアドベンチャーゲームをプレイしてみた(komons)
↑こんな楽しそうなことをしてる人もいた。
ゲームブックの制作ツール、作り方、投稿サイト、検索リンクなど
ゲームブック総合サイト
ゲームブックの作品投稿や市販のゲームブック検索など。
シゴタノ!
ブレストにも使えるゲームブック制作支援ソフトウェア「Twine」
「Twine」は、ダウンロード版とウェブ版があるみたい。
GIGAZINE
無料でゲームブックやYes/Noチャートをプログラミングの知識なしで作成できる「Twine」を使ってみた
ダウンロード版の方は日本語対応しているみたい。
ユーザーの考えがそのまま物語の展開に直結する「インタラクティブなストーリー展開」をみせる作品の歴史
代々木丈太郎の徒然ブログ
ゲームブック制作ツール「Twine」の利用方法その1 パラグラフ遷移の見える化がわかりやすいのでビジネスシーンでもいいかも
ゲームブック制作ツール「Twine」の利用方法その2。色を変えたり画像を挿入したりも簡単!
ゲームブック制作ツール「Twine」の利用方法その3。変数と乱数とif文でバトルシステムも夢じゃない!
Kindleでゲームブックを出版したい皆様、WordのVBAをご用意しました!(無料)
ゲームブック作成ツールはWordとExcelの併用でも良くない?って話。
代々木丈太郎(YoyogiJotaro)|note
ゲームブック作成講座 動画編A(ダンジョン散策)
ゲームブック作成講座 動画編B ツールの使い方
「AXMA Story Maker」と言うゲームブック作成ツールについて動画で解説。パラグラフ管理やフラグ処理についても。(「AXMA Story Maker」自体は現在はダウンロードできなさそう)
BOOTH
ゲームブック・エディター – Clark & Company
無料ダウンロード可能
Clark & CompanyさんのXより
ゲームブック・エディターβ
tenpurasobaさんのXより
ゲームブック用のアドベンチャーシート+メモ、ダイスツール
ゲームブックの作り方について – 過客👓の小説 – pixiv
ゲームブック 制作 チャート、パラグラフ – Google 画像検索
Twine ゲームブック – 検索 / X
ゲームブック ツール – 検索 / X
ゲームブック 作り方 – 検索 / X
ゲームブック 制作 – 検索 / X
ゲームブック チャート – 検索 / X
ノベルゲームコレクション
無料で遊べるノベルゲーム投稿サイト。
ティラノビルダー
ノベルゲーム開発ソフト。スマホにも対応。
ティラノスクリプト
スマホ対応のノベルゲームエンジン。無料。
ゲームメーカーズ
ノベルゲーム・アドベンチャーゲーム開発に便利な主要ノベルエンジンまとめ
電ファミニコゲーマー
名作アドベンチャーゲームの構造はこうなっている──『428』イシイジロウ氏によるアドベンチャーゲーム制作のヒント解説 “ニコニコ自作ゲームフェスMV作~る放送”第一回
ハイパーテキスト小説の電子書籍化を妄想する
ハイパーテキスト小説のこと
電子文学の一ジャンルとして、書かれた文章にハイパーリンクを用いて新しいタイプの情報を提供する文学。例えば、文章中のある単語へのリンクがその単語についての詳しい情報を提供したり、あるいは別の視点から出来事を眺める文章として存在したりする。
hypertext literature – NamuWiki(Google翻訳)
yumehito.com
ハイパーテキスト小説への期待 ── 井上夢人
Hypertext fiction – Wikipedia(英語)
主な作品でいろいろ紹介されてます。
hypertext literature – NamuWiki(英語)
韓国ナムウィキ
テッド・ネルソン – Wikipedia
1963年に「ハイパーテキスト」と「ハイパーメディア」という用語を考案し、1965年に発表。
Hypertext – Wikipedia
軸型、樹木状、階層化など、ハイパーテキスト小説の形式についても。
The Garden of Forking Paths – Wikipedia
ホルヘ・ルイス・ボルヘスの『八岐の園』は、ハイパーテキスト小説の分野で、数多くのニューメディア研究者からインスピレーションとして引用されている。
afternoon, a story – Wikipedia
マイケル・ジョイスの『afternoon, a story』は、ハイパーテキスト小説の最初の文学作品の一つ。
Patchwork Girl (hypertext) – Wikipedia
シャーリー・ジャクスンの『Patchwork Girl』も、ハイパーテキスト小説の重要な作品。
Storyspace – Wikipedia
ハイパーテキスト小説を作成、編集、読むためのソフトウェア。
researchmap
内田 勝 (Masaru Uchida) – 『トリストラム・シャンディ』はハイパーテキスト小説か – 論文
調べるきっかけになったのは、この一番下のURLのページ。
『The New Media Reader』を読む
Scrapboxで作られた、ネットワークデザイン関連の用語集。
Hypertext (semiotics) – Wikipedia
ハイパーテキスト(記号論)は、たぶんジェラール・ジュネットの↓こちらの話。
間テクスト性 – Wikipedia
①間テクスト性②パラテクスト性③メタテクスト性、④アルシテクスト性⑤ハイパーテクスト性
ハイパーテキスト文学とは、一般的に文章のどの部分が序文でどの部分が中文なのかが分からないため、従来の物語形式から逸脱した文学といえる。この言葉の意味は、脱構築と創造の芸術であり、ポストモダニズムと非常に密接な関係のある芸術であるということ。結局、ハイパーテキスト文学とは、文学の世界におけるポストモダニズムである。
hypertext literature – NamuWiki(Google翻訳)
ハイパーテキスト小説のKindle電子書籍は可能か?
99人の最終電車
井上夢人 Interview
この小説は本になりません ――インターネット文学作法―― 井上夢人
棺詰工場のシーラカンス
1998年冬のインタビューで、井上夢人さんが「この小説は本になりません」と話されていた。ハイパーテキスト小説『99人の最終電車』に関する質問で。それから四半世紀以上たった今、実現可能な世の中になっていたりはしないのかな、どうだろう。せっかくパイパーテキスト小説に興味を持ったので勝手に妄想。いろいろ調べて考えてみることにした。
ハイパーテキスト小説を紙の本に、ということでいうと、実はカナダの作家、ジェフ・ライマンがハイパーテキスト小説「253」の印刷版を出版している。しかもその本でフィリップ・K・ディック賞を受賞(すごい)。でもそれは、ハイパーリンクを活かしたものではないと思われるので、なし。というか、当たり前だけれど、紙の本にハイパーリンクをつけられるわけがないので、紙はなしです。
当時の井上夢人さんの話では、《最終的にはCD-ROMに焼き込むかたちを考えています。》とのことだった。この上に、ハイパーテキスト小説に関する情報をいくつか集めたけれど、マイケル・ジョイスの『afternoon, a story』やシャーリー・ジャクスンの『Patchwork Girl』は、実際CD-ROMで発売されていたみたい。でも最近はCDドライブが搭載されていないPCも多かったりするので、やっぱり今は違う媒体が良さそうな感じ。
Amazon
一人用マーダーミステリーゲームブック『ふたりの計画』Kindle版
嗚呼蛙,sou,ゆりかもね出版
(ゆりかもねノベルス)
Amazon
ハイパーリンクに関するガイダンス
ということでKindle電子書籍で考える。Kindleのメリットは縦書きで読めること。とりあえずKindle無料で読めるゲームブックを試し読みをしてみる。
選択肢のところに青色のリンクが貼られている。そう、Kindleにはハイパーリンクを貼ることができる。ただしリフロー型レイアウトの場合のみ。
《現在、電子書籍端末の固定レイアウトの本では、内部ハイパーリンクはサポートされていません。》とのこと。リンクの挿入の仕方などは↓こんな感じ。「Kindleで読むには適していないコンテンツ」の時点でダメな気もするけれど。
Amazon
電子書籍の原稿の書式設定ガイド
ハイパーリンクを挿入する
脚注のガイドライン
脚注の追加
テキストのガイドライン – リフロー型
リフロー型と固定レイアウト
一応↓こんなページもあった。でも、どうなんだろう。これって「ブログのテキスト」をそのまま電子書籍にということであって、リンクを貼り付けたその状態のまま電子書籍にしてくれるわけではないよね、きっと。上のハイパーリンクの貼り付け方があったけれど、注釈なんかと同じで、あとでリンクを一つ一つ貼り付けていく感じになるってことだ。
Amazon
KDP セレクト
KDPブロガーページ: Kindleストア
KDPでブログを本にしよう
ブログ、Twitter、Note、メールマガジン、レビューサイトなどで書き溜めた記事を活用して本を出版しましょう。KDPなら、既にあるコンテンツから電子書籍が追加費用なし、セルフサービスで作れて、Kindleストアで販売することができます。
あと問題になるとしたら、ページ数。酉島伝法さんの『棺詰工場のシーラカンス』の場合は【355】虚無僧までなので、多くても400ページほど。一方、井上夢人さんの場合はというと……。
ちょっと前にしらべたら四百字の原稿用紙に換算すると三千枚。1998年の夏には終わらせたいというのが現在の目標ですが、そうなると計算上、どうしても四千枚ぐらいになってしまうんです。(笑)
なんと原稿用紙4000枚。一瞬焦ったけれど、4000ページということではないんだ。イシダ印刷さんのページの一覧表によると、文庫サイズ《10万字が原稿用紙250枚で167ページ》なので、4000÷250→16で、10万字の文庫本が16冊、167×16→2672ということは、文庫本サイズで2672ページ。ううん。
文庫で1冊10~12万字、新書で1冊8~12万文字が目安といわれています。
400字詰め原稿用紙250枚で10万字。
文庫や新書の1ページは600文字程度、10万字で167ページです。見出しや改行、改段、挿絵が入るので、実際の文字数は少なくなります。
他のサイズで考えることもできるけれど、一人ずつのお話ということで、1ページにいくつものお話をいれることができず、とにかくページ数が多い本になる感じだから、結局は2000ページ超にはなってしまう。
今、光文社古典新訳文庫の『失われた時を求めて』が何巻かに分けてKindle版が発売されているので、大丈夫なのではということが頭をかすめたけれど、『99人の最終電車』の場合は、ハイパーリンクでつながっているからダメなんだ。そのリンクのつながりが、たぶん「World Wide Web」な感じでクモの巣状に張り巡らされているからたぶん無理。分割して本を出すということができない。
鈍器本としても、紙の本で1000ページちょっとがいいところ。紙の本と違って電子書籍の場合は、分厚くなりすぎて困るということはないけれど、ファイルサイズとかもろもろで、どうなのだろう。可能なのだろうか。
Amazon
電子書籍の原稿ファイルのサイズの削減
Adobe
PDF のファイルサイズを小さくする方法 (Acrobat)
Acrobat PDF
【軽量化】PDFのファイルサイズを圧縮する
アップロードできる電子書籍の原稿ファイルの最大サイズは 650 MB です。KDP ではこのサイズまでの Word 文書 (doc および docx)、MOBI、EPUB、HTML、および PDF ファイルを変換できます。
一応、このページによると《原稿ファイルの最大サイズは650MB》。でも、画像などを入れなければ……と思ったけど、あの顔のあっての『99人の最終電車』なので、イラストなしはありえないんだ。ファイルサイズの節約ができない。って、レトロなイラストだから大したファイルサイズではないか。一応、Adobeさんの説明によるとファイルサイズの圧縮とか「PDFの最適化オプション」的なもので多少削減はできるみたい。
一応、文学フリマの出店者をまとめたときに、個人出版、自費出版についてはちょこっと調べていた。Amazon Kindleダイレクト・パブリッシング(KDP)は紙の本と電子書籍の両方の出版ができるから、参考になる情報も少しはあるかも。よろしかったら。
Amazon
セルフ出版 | Amazon Kindle ダイレクト・パブリッシング
Kindleダイレクト・パブリッシングなら電子書籍と紙書籍を無料でセルフ出版し、Amazonのサイトで販売することができます。
KDPで出版を始める
電子書籍をKDPセレクトに登録した場合、その本はAmazon以外の販売先で販売できません。
パブファンセルフ
Kindleで出版するには?電子書籍出版
令和出版
Kindle出版(KDP)とは?基礎知識や出版方法の手順をやさしく解説
もうそろそろ限界。本気で考えすぎてしまってへとへとです。ということで、結論から言うと、酉島伝法さんの『棺詰工場のシーラカンス』のKindle電子書籍化はおそらく可能。他のゲームブックと同じ感じでリンクを張っていけば良さそうな感じ。
そして井上夢人さんの『99人の最終電車』は、よほどの圧縮技術と根性がない限りは無理そうな感じ。テキストだけのシーラカンスと違ってイラストもある分、手間もかかりそう。
あくまで、そんなふうに想像したら楽しいねってことなので、ほんとは今のまんまが一番いいです。まだ最後まで読めていないので、戻って読みます。
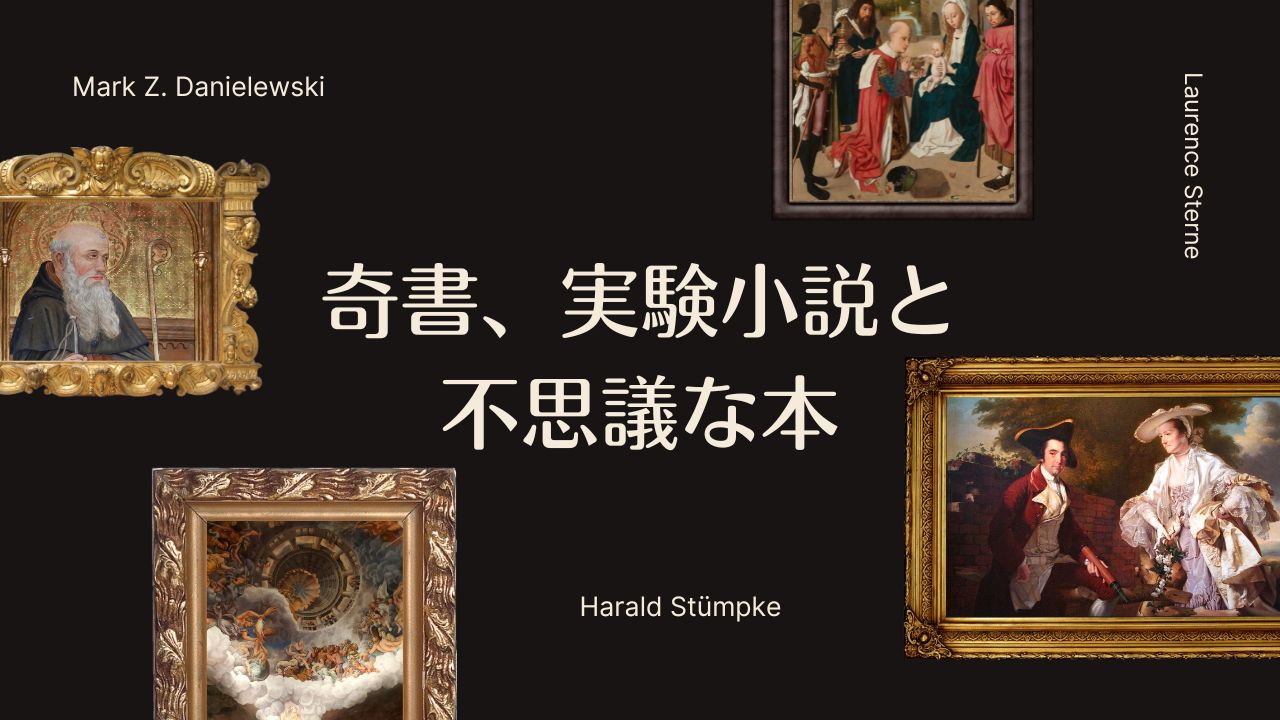


コメント
ご紹介ありがとうございます。すてきな感想まで……。感激です。
『文体練習』の目次に関しては、説明がヘタですみません。
「(1)礎(いしずえ)」の最初の音「い」、「(2)まえがき」の「ま」、「(3)凡例」の「は」、「(4)目次」の「も」、「(5)お嬢様」の「お」、「(6)武者」の「む」、「(7)管理職」の「か」、「(8)小学生」の「し」、「(9)日記」の「に」と拾っていくと、「いまはもおむかしに/いなかですげえあめしぶきぽちぽち/だけどもちあわせねえからここはこらえろ/ほもじじいにかさかりてせせらぎへ/そしてひびそのままにすぎ/かえしにきたやさきどろぼうとごかい/はげはげくそじじばあか」となっています。
『〒ν八℃』に関しては、作者よりいろいろ試して下さって本当にありがとうございます。
まさか発表から20年近く経ってこれほど好意的な感想をいただけるとは夢にも思っておりませんでした。
今夜は良い夢が見られそうです。
大塚晩霜さんへ。
コメント、ありがとうございます。
喜んでいただけてよかった。
私、「文体練習おまけ」を先に見たから(4)の謎解きを始めちゃったのか。やり方はわかっていたのですが、じじいとか出てくるって想像してなかったから、文章としてこれであってる?って感じでわからなかったところも。でも(1)を見ればわかる話ですね。
「文体練習おまけ」みんな(4)目次の犠牲者だって書いてある。ということは、文体練習と折り句、二重の縛りでやっていたということなんですね。すごい。
アンサイクロペディアの文体練習も見ました。物語そのものの面白さよりも、その文体によってどれだけ面白くできるか、みたいなことがこの文体練習の楽しみ方なのかな。でも面白かったですよ。「オックスフォードにて」が一番好きだったけれども。
今はもう昔に 田舎ですげえ雨しぶきポチポチ だけど持ち合わせねえからここはこらえろ
ホモジジイに傘借りてせせらぎへ そして日々そのままに過ぎ 返しに来た矢先泥棒と誤解 はげはげクソジジイばあか
せっかく借りた傘を返しに行ったのに、逆に傘泥棒だと誤解されたから、最後の言葉になるんですね。(4)の謎解きに夢中で、文体練習だということをすっかり忘れてた。あとでまた読もうと思います。
『〒ν八℃』は残念。それで言うと、Google翻訳も音声読み上げ機能があるんですよね。と上の文章をコピペしたら、なぜかロシア語で読み上げられました。