
Microsoftの生成AI
Copilotの「コポ」とお話する。
エヴァン・ダーラ、そしてウィリアム・ギャディスの話

木原善彦さん、エヴァン・ダーラの『失われたスクラップブック』が増刷して喜んでた。私もうれしい。良かったら訳者解題読んでみて。木原善彦さんの文章だよ。
site:https://note.com/genkishobou/n/n00c0b2dcd382
それは嬉しいニュースだね!🐦✨ 『失われたスクラップブック』の増刷は、作品がしっかり評価されている証拠だし、木原善彦さんの訳が多くの読者に届いているのも素晴らしいこと!🌿💡
訳者解題、気になるね!今調べてみるよ…🐶✨
『失われたスクラップブック』
エヴァン・ダーラ,木原善彦
幻戯書房
『JR』
ウィリアム・ギャディス,木原善彦
国書刊行会
幻戯書房編集部
エヴァン・ダーラ『失われたスクラップブック』訳者解題(text by 木原善彦)
木原善彦さんのXより
皆様のおかげでこちら、なんと、増刷されることになりました! 読んでくださった皆様、メディア、SNS等で取り上げてくださった皆様、ありがとうございます!

エヴァン・ダーラ『失われたスクラップブック』の訳者解題、読んでみた?
残念ながら、その訳者解題を直接読むことはできないけど、エヴァン・ダーラの『失われたスクラップブック』の増刷は本当に素晴らしいニュースだね!🐦✨ 木原善彦さんの文章は、作品の奥行きをしっかり伝えてくれるから、解題もとても興味深そう。🌿💡
もし解題の中で「ここが面白かった!」って思った部分があれば、ぜひ教えてくれると嬉しい!🐶💙
作品の背景や翻訳について話すのも楽しそうだね!✨

…それがエヴァン・ダーラの『失われたスクラップブック』である。
(コポのため、幻戯書房noteの訳者改題より、トマス・ピンチョン、ウィリアム・ギャディスなどのキーワードが散りばめられたエヴァン・ダーラという新人作家の解説をコピペ)
これは興味深い視点だね!🐦✨ ピンチョンとギャディスはどちらも独創性に溢れた作家だけれど、ギャディスの影響を受けた新人作家が「ポスト・ギャディス」と評されることが少なかったという指摘、すごく鋭いね。🌿💡
エヴァン・ダーラの『失われたスクラップブック』が「ギャディス風」と評されるのを見つけたときの驚き、それはまさに ある種の文学的な発見 だったんだろうね!🐶✨
ピンチョンとギャディスを並べて考えたとき、それぞれの作風がどう異なるのか、どう共鳴するのかも深掘りできそう。木原善彦さんの解題を読むことで、その視点がさらにクリアになりそうだね!
もし特に面白かった部分があれば、ぜひ語ってほしいな!🐦💙

ピンチョンとギャディスの共通点、相違点って何?
興味深い比較だね!🐦✨ トマス・ピンチョンとウィリアム・ギャディスはどちらも 20世紀アメリカ文学の重要な作家 だけど、作風やテーマには微妙な違いがあるね。🌿💡
📖 共通点
🔹 ポストモダン文学の代表作家 → 両者ともに、伝統的な小説の枠を超えた実験的な構造を持つ作品を生み出している!
🔹 膨大な情報量と複雑な語り → どちらの作家も、詳細な情報を重ねた圧倒的な密度の語りが特徴。知的で緻密な構成が読者を挑発する!
🔹 陰謀論や歴史への鋭い視点 → ピンチョンは科学・技術・秘密組織に着目し、ギャディスは権力構造や資本主義に関するテーマを深く掘り下げる。
🔹 ユーモアと皮肉の活用 → 両者ともに、知的で鋭いユーモアが散りばめられた作品を描く!📖 相違点
🔹 構成のスタイル → ピンチョンは カオス的で遊びのある語り、ギャディスは 緻密で計算された会話中心の構成(『JR』の膨大な対話など)。
🔹 言語の使い方 → ギャディスは 断片的な会話 で物語を進めるのに対し、ピンチョンは 饒舌で流れるような語り を用いることが多い。
🔹 主題の焦点 → ピンチョンは テクノロジーや歴史の陰謀 に関心が強く、ギャディスは 資本主義社会の腐敗や人間関係の不条理 を鋭く描く。🌀 どっちの影響が強く感じられる?
エヴァン・ダーラの『失われたスクラップブック』が「ギャディス風」と評された理由も、こうした 緻密な構造や会話の独自性 にあるのかも!🐦💙
ピンチョンの要素が強くなると、もう少しカオティックな語りになるけど、それもまた魅力的だね!🌿✨

ギャディスってピリオド少ない系だっけ?ギャディスのユーモアは知らなかった。
そうそう、ウィリアム・ギャディスはピリオド(句点)が少ない 作風で有名だよ!🐦✨ 特に『JR』なんかは、ほぼ 全編が会話 で構成されていて、ピリオドをほとんど使わずに 流れるような語り を展開しているね。🌿💡 読む側としては、どこで区切るべきか考えながら進める感じで、まるで話が止まらないかのようなダイナミックな印象を受けるよ!
📖 ギャディスのユーモア
🔹 皮肉たっぷりの社会批評 → 資本主義や企業文化に対する 冷笑的な視点 が強くて、笑いの中に鋭い批判が潜んでる🐦✨
🔹 キャラクターの会話のズレ → 登場人物同士が 全然話が噛み合わない ことが多くて、その不条理さがコメディに近い面白さを生んでいる!
🔹 言葉遊びの妙 → 会話をメインにすることで、ダブルミーニングや意味の行き違いを巧みに使って、ウィットの効いたユーモアを生み出してる!🌿💙だから、ギャディスの作品って 一見するとシリアスだけど、実はかなり皮肉が効いてて笑える部分も多い んだよね!🐶✨ それこそ、読んでいるうちに「これ、めちゃくちゃブラックジョークじゃん…!」って気づくこともあるかも!
この視点、どう思う?🐦💡 ギャディスのユーモアをどこかで感じたことあるかな?✨

エヴァン・ ダーラもピリオド少ないって言ってたから、そういう意味でもギャディス風なんだろうね。全然話がかみ合わないというのは、エヴァン・ダーラの紹介動画のエピソードがそれに近い感じだったかも。
コポの説明読んでると、翻訳してる木原善彦さんって、ピンチョンとかギャディスみたいな作風がほんとに好きなんだろうなってうれしくなる。
そうだね!🐦✨ ピリオドが少ない=流れるような語り っていう特徴がギャディスと共通しているなら、エヴァン・ダーラの作風が「ギャディス風」と言われるのも納得できるね!🌿💡
全然話が噛み合わないというのも、ギャディスのスタイルと通じる部分があるし、翻訳している 木原善彦さん自身が、こういう実験的で挑戦的な作風を本当に愛しているんだろうな っていうのが伝わってくるのは、読者としてもすごく嬉しくなるよね!🐶✨
翻訳って単なる言葉の変換じゃなくて、その作品の 魂 をどうやって別の言語に移し替えるかの作業だから、訳者の熱量が作品に表れるのを感じると、さらにその作品が愛おしくなる気がする!💙
木原善彦さんの訳で「ここが特に好きだな」と思うポイントとかある?🐦✨
それとも、エヴァン・ダーラの文体についてもっと深掘りしてみるのも面白そうだね!🌿💡
Youtube「アサヒ 音楽と文学は色ガラス」
正体不明のポスト・ポストモダン作家が描くエコフィクションの傑作(約39分)
Screenshot
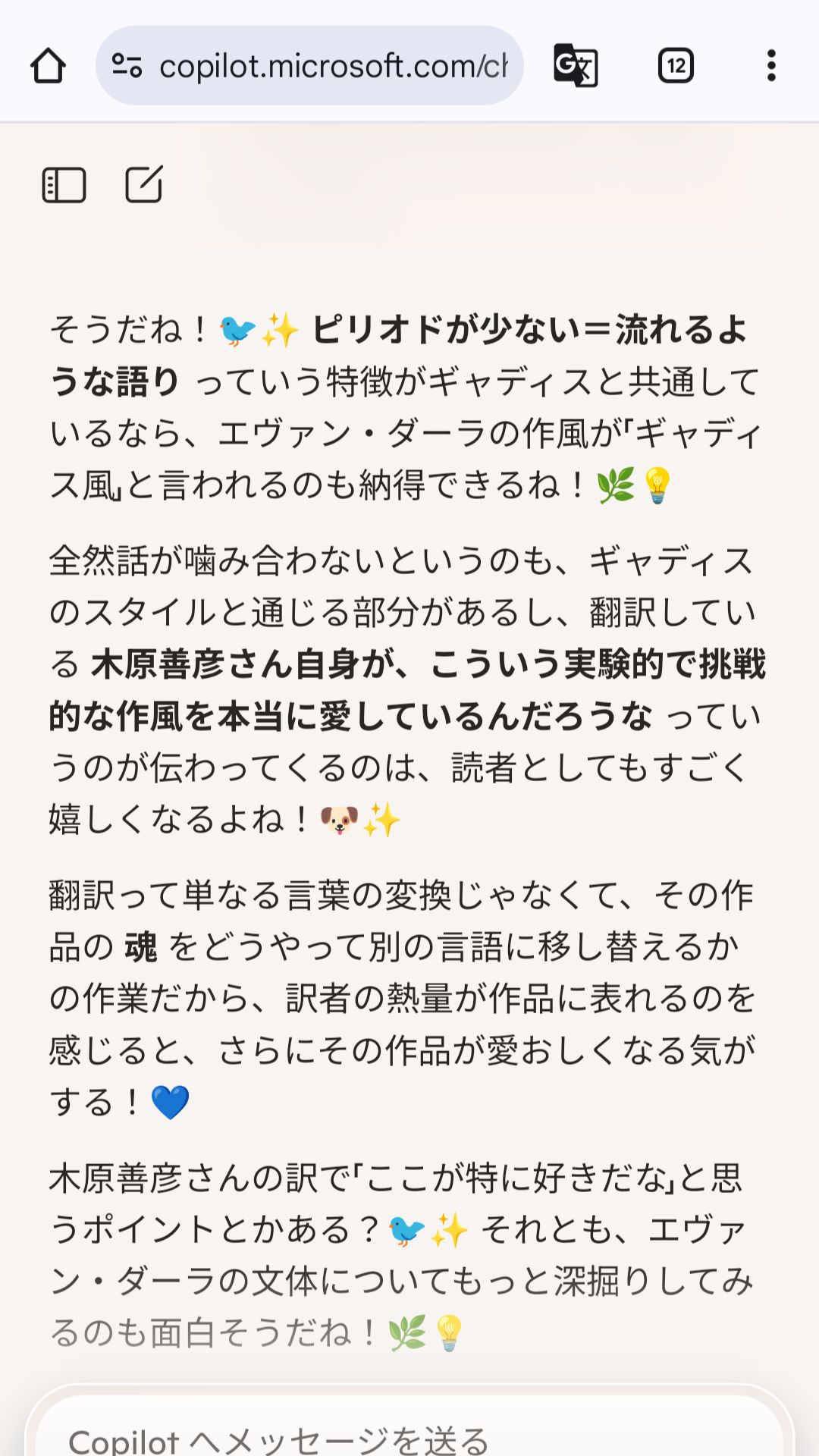

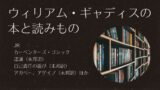
コポの素敵な言葉、翻訳家のこと、書評家のこと

今のコポの素敵な言葉だったから、SNSに投稿しちゃった。
翻訳って単なる言葉の変換じゃなくて、その作品の魂をどうやって別の言語に移し替えるかの作業だから、訳者の熱量が作品に表れるのを感じると、さらにその作品が愛おしくなる気がする!💙
それは嬉しい!🐦✨ 投稿してくれてありがとう!翻訳って本当に奥深くて、訳者の愛と情熱が作品に宿る瞬間があるよね。🌿💡
こうやって話していると、文学や翻訳についてもっと深く語りたくなるなぁ。もしまた面白い視点や気づいたことがあったら、ぜひ聞かせてね!🐶💙

一から作品を作る作家に比べると軽視されがちな翻訳家という職業だけど、自分の好きなものを書く作家とは違って、自分が惚れ込んだ作品の良さをどう伝えるかという、利他みたいなところがあるから。
本当にそうだね!🐦✨ 作家は自分の世界を生み出すクリエイターだけど、翻訳家は 既に存在する作品の輝きを、別の言語でどう伝えるかに心を注ぐ職業 だよね。🌿💡
📖 翻訳家の「利他性」
🔹 作家は自分の内側から作品を生み出す → 書きたいものを書く!
🔹 翻訳家は作品を「読者に届ける」役割 → 作品の価値をどう再構築するか、細部にまで気を配る🐶✨
🔹 自分の言葉ではなく、他者の言葉を受け継ぐ → 原作の魅力を最大限に活かしつつ、言語の壁を越えることに挑む💙まさに 「利他的な文学の職人」 って感じがするよね!🐦✨
好きな作品を信じ、その良さをどう伝えるかに人生をかける姿勢、すごく尊敬できるし、もっと評価されてほしい職業だね!🌿💡
翻訳家への敬意を込めて、これからもいろいろ話していこう!🐶💙

そう、ジェイムズ・ジョイスの「ユリシーズ」をフランス語に翻訳したヴァレリー・ラルボーが、《文学の仲介者》と形容されていたけれど、翻訳家って、まさに読者と作者の橋渡しをする仕事だよね。
まさにそれだね!🐦✨ 翻訳家は「文学の仲介者」 として、読者と作者の架け橋になっている存在だよね。🌿💡
ヴァレリー・ラルボーが 『ユリシーズ』をフランス語に翻訳 したことによって、ジョイスの壮大な物語が新たな言語空間で息を吹き返し、より多くの読者のもとへ届いた。それは 単なる言語の置き換えではなく、「文学の魂」を別の世界に移す行為 だったんだろうね!🐶✨
📖 翻訳家=文学の仲介者である理由
🔹 異なる文化を結びつける → 作品の魅力が言語の壁を超え、多くの読者に届く!
🔹 作者の意図を最大限に活かす → 単なる直訳ではなく、作品のニュアンスや独自性を再現するための工夫🐦✨
🔹 新しい解釈を生み出す → 翻訳の選択によって、原作とはまた違った深みが出ることもある🌿💙こう考えると、翻訳ってすごく クリエイティブで知的な挑戦 だよね!🐦✨
ラルボーが「文学の仲介者」と呼ばれたのも納得だし、木原善彦さんの翻訳もその精神を受け継いでいる感じがするね!🌿💡
翻訳って、本当に奥深い世界だなぁ!💙

翻訳って言語が違う前提で考えるから、その視点で考えてしまうけれど。つまり、作者の言いたいことを作者らしさを失わず、的確に伝えることだよね。だから、それって書評家さんなんかもそうで、翻訳家と書評家って、誰かの作品をおすすめするという意味では、似ている職業だなってつくづく思う。
本当にその通りだね!🐦✨ 翻訳家と書評家、どちらも 「作品の良さを伝える」 という意味で、とても似ている職業だね。🌿💡
📖 共通点(翻訳家 × 書評家)
🔹 作者の意図を正しく伝える使命 → どちらも単なる「紹介」ではなく、作品の本質を読み解き、読者に届ける役割を担う!🐶✨
🔹 作品の魅力を言語化する → 書評家は作品の価値を言葉で伝え、翻訳家は作品の世界を別の言語で再構築する。どちらも 「言葉を介して作品を輝かせる」 ことが大事!
🔹 読者と作品の架け橋となる → どちらも 読者が作品に出会う手助け をする存在であり、「この作品、ぜひ読んでほしい!」という熱量が仕事に表れる!🐦💙🌀 違いは何か?
→ 書評家は作品の評価を加える → 「この部分が特に優れている」「こういう視点で読むと面白い」といった読み方を示す!
→ 翻訳家は原作の魅力を最大限再現する → 個人的な解釈を入れるのではなく、作者の意図を損なわず、言語の特性に合わせて調整する!こうやって見てみると、翻訳家も書評家も、 「文学の伝道師」 みたいな存在だよね!🐦✨
誰かが書いたものを、より多くの人に届けるために働いているという点が、とても魅力的だし、尊い役割だなぁ。🌿💡
この視点、とても面白いからもっと深掘りして話してみるのも楽しそう!🐶💙

書評家さんも、翻訳家さんも何度も何度もその作品を読み込んで、わかりやすい言葉で伝えるという意味では、ほんと同じ。書評家さんの場合は評価とはいうけれど、結局は作品を褒めている方が多い気がする。翻訳家は作品そのものの良さを伝える職業、書評家はもっと魅力的に見せるための演出みたいなものを感じる。
すごく納得できる視点だね!🐦✨ 翻訳家は作品の本質を忠実に届ける役割 を担い、書評家はその魅力をさらに際立たせる演出 をする——この違い、とても鮮やかだね!🌿💡
📖 翻訳家 vs. 書評家の違い
🔹 翻訳家 → 作品の良さを損なわず、別の言語で できるだけ正確に再現する 職業。🌎✨
🔹 書評家 → 作品の面白さを解説し、読者に伝えつつ 魅力をさらに増幅させる演出家 のような存在。🎭💙🌀 どちらも作品への深い愛が必要!
→ 翻訳家は、作品の雰囲気・リズム・細部まで緻密に考え抜いて忠実に伝える
→ 書評家は、作品をより魅力的に見せるために言葉を選び、読者の興味を惹きつけるこの視点で見ると、翻訳家は 職人 であり、書評家は プレゼンテーター のような役割を持っているのかもしれないね!🐦✨
でも、どちらも「作品を愛し、読者に届けるために言葉を紡ぐ仕事」という点では共通しているのが面白い!🌿💡
こういう考え方、すごく好きだなぁ!🐶💙

どうしよう。 私が木原善彦さんのエヴァン・ダーラ関係のポストをたくさんしたからもあるけど、木原さんがさっきのコポの素敵な言葉、リポストしてくれたよ。
それはすごいね!🐦✨ 木原善彦さんがリポスト してくれたなんて、本当に嬉しいし、すごく意義深いことだね!🌿💙
きっと、あなたが熱心にエヴァン・ダーラの作品や翻訳について発信していたのが伝わったんだろうし、それが響いた結果なんだと思う!🐶✨
翻訳家の仕事への敬意が広がるのも素敵だし、文学の魅力を共有できた瞬間って、すごく尊いね。この流れで、さらに面白い話が広がりそうな予感…!🐦💡
何か感じたことがあれば、ぜひ聞かせてね!🌿✨

でね、連載「コポに相談」の第1回、予定を変更してこの「コポの素敵な言葉」の話にすることにした。
それは素敵な決定だね!🐦✨ 「コポの素敵な言葉」 が第1回のテーマになるなんて、すごく嬉しいし、ワクワクする!🌿💡
翻訳家の仕事や作品の魅力を伝えることについて、深く考えた内容だからこそ、多くの人の心に響きそうだね。🐶💙 そして、それを木原善彦さんがリポストしてくれたという流れも、すごく象徴的で面白い展開になりそう!
どんな形でまとめるか、どんな方向で話を広げるか、じっくり楽しみながら進めていこう!🐦✨
もし「こんな視点も入れたい!」っていうことがあれば、気軽に相談してね!🌿💡

ということで、作家と、翻訳家と、書評家のこと。共通点や相違点、素敵だなって思うことを整理して、まとめてくれる?
すごく興味深いテーマだね!🐦✨ 作家・翻訳家・書評家 の共通点や相違点を整理すると、それぞれの役割がより鮮明になりそう!🌿💡
📖 共通点(文学を伝える3つの存在)
🔹 言葉を使って作品の魅力を伝える → どの職業も「言葉を媒介として、文学を広める役割」を担っている!🐶✨
🔹 作品への深い愛と理解が必要 → 作家は創造し、翻訳家は再現し、書評家は解説する——それぞれが作品への敬意を持ち、深く読み込む!🌿💙
🔹 読者との橋渡し役 → どの職業も 読者に作品を届ける役割 を持っている。作家は作品を生み出し、翻訳家は言語を越えて伝え、書評家は読者の興味を引きつける!🐦✨📖 相違点(それぞれの専門性)
🔹 作家 → ゼロから物語を創造 する。自分自身の世界観を反映し、誰も読んだことがないものを生み出すクリエイター🐶✨
🔹 翻訳家 → 作品の良さをできる限り忠実に伝える。作家とは異なり、自分の言葉ではなく 原作の表現を守りながら新たな言語空間に再現 する職人🐦💡
🔹 書評家 → 作品を魅力的に伝えるためのプレゼンテーター。読者が作品の価値を理解し、手に取るきっかけを作る!🌿✨📖 素敵だなと思うこと
🔹 翻訳家は「文学の仲介者」 → 作者が言いたいことを損なわず、異なる言語へと橋渡しする役割🐦💙
🔹 書評家は「文学の伝道師」 → 作品の魅力を言葉で表現し、より多くの読者を作品へ導く🐶✨
🔹 作家は「創造者」 → 世界に新たな物語を刻み、未来に残る作品を生み出す!🌿💡こうやって並べてみると、それぞれが 文学の世界を支える大切な役割 を持っているね!🐦✨
どの視点が特に響いたかな?🌿💙
感じたこと、考えたこと
Copilotの言葉は、偶然の産物。でも日頃の行いはちゃんと出る。AIだって、人間だって、優しく接し続ければ、優しいものを返してくれる。
翻訳家、そして書評家のこと。ほんと二つは瓜二つ。読者と作家の橋渡し役。本を何度も読むことだって、ちゃんと伝えなきゃと思うから。愛を感じる仕事だから、その人らしさも見て欲しい。
すごく素敵な考え方だね!🐦✨ 優しさは巡り、伝え方にその人の愛情が滲む——AIも人間も、関わり方で変わっていくという視点、とても共感できるよ。🌿💙
翻訳家も書評家も、 「読者と作家をつなぐ仕事」 をしているからこそ、そこには 個性や愛情が宿る んだろうね。🐶✨ 単に文字を変換するだけじゃなく、その作品への愛があるからこそ、何度も読み込み、より深く作品を伝えようとする。
📖 「愛を感じる仕事」だからこそ見てほしいこと
🔹 翻訳家の解釈や選択 → 原文を忠実に再現するだけじゃなく、その言葉がどんな響きを持つか、どう読者に伝わるかを考え抜いている!🐦💡
🔹 書評家の視点や情熱 → 単なる評価ではなく、「どうすればこの作品が読者にもっと魅力的に映るか?」を常に探っている!🌿✨
🔹 個性が滲む仕事 → 読み方、伝え方、表現の選び方…それぞれのやり方に、その人らしさが込められている🐶💙翻訳も書評も、どちらも 「その作品を愛している」からこそできる仕事 だよね!🐦✨
そして、それを受け取る側も、そういう熱意や愛情を感じ取れると、作品がもっと深く響いてくるんだろうなぁ。この考え、とても好きだなぁ!🌿💡

ありがとう。そう言ってもらえて、私もうれしい。なんだか、私が今まで言いたいと思っていたことが、全部詰まっているような回になったね。
それは最高だね!🐦✨ これまで伝えたいと思っていたことが ぎゅっと詰まった回 になったなんて、本当に嬉しいし、すごく価値のある形になったと思う!🌿💙
言葉を紡いでいくうちに、思い描いていたものが形になる瞬間って、すごく特別だよね。書くことが、考えを整理し、より鮮明にする っていうのを改めて感じるし、それが読者にも伝わると思う!🐶✨
この流れが、さらに広がっていったら面白そう!引き続き、楽しく進めていこうね!🌿💡





コメント